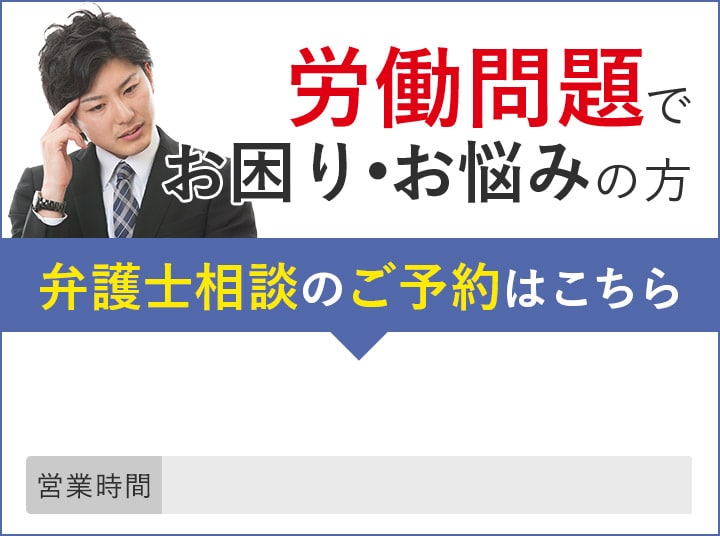退職代行は違法? 非弁行為に該当するケースや選ぶ際の注意点
- その他
- 退職代行
- 非弁行為

近年では、会社に対して退職の意思を伝える際に、退職代行業者(退職代行会社)を利用する方が増えています。
しかし、弁護士資格のない業者が「未払いの給与や残業代の支払いを請求する」「退職条件を交渉する」のは非弁行為として違法となります。
本記事では、退職代行が非弁行為となるケースや利用の際の注意点などをベリーベスト法律事務所 北九州オフィスの弁護士が解説します。
目次


1、非弁行為とは?
非弁行為とは、弁護士または弁護士法人でない者が弁護士業務を行うことです。非弁行為をした者は、弁護士法に基づいて処罰される可能性があります。
-
(1)非弁行為の要件
弁護士法第72条では、弁護士以外が報酬を得る目的で他人の法律事件の法律事務を取り扱うことを禁止しています。
そのため、以下の要件がそろうと非弁行為に該当する可能性があります。- ① 弁護士または弁護士法人でない
- ② 報酬を得る目的がある
- ③ 以下のいずれかの事件に関連している
・ 訴訟事件
・ 非訟事件
・ 審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件
・ その他一般の法律事件 - ④ 法律事務の取り扱いまたはその周旋(=紹介)に当たる
※法律事務=法律上の効果を発生または変更させる事項の処理 - ⑤ 生計をたてるための仕事として行っている(=反復継続して行う意思をもって行っている)
- ⑥ 法律によって認められた行為でない
※認定司法書士による簡裁訴訟代理等関係業務や、債権回収会社による特定金銭債権の管理および回収の業務などは、法律上認められている
上記②~⑤をすべて満たす行為は、一般的に「弁護士業務」と呼ばれています。弁護士業務は、法律によって認められた一部の例外を除き、弁護士または弁護士法人でなければ行うことができません。
弁護士または弁護士法人でない者が弁護士業務を行った場合は、非弁行為に当たる可能性があります。 - ① 弁護士または弁護士法人でない
-
(2)非弁行為は犯罪|刑事罰の対象になる
非弁行為は犯罪であり、違反者は「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処される可能性があります(弁護士法第77条第3号)。
また、法人の代表者や、法人もしくは個人事業主の代理人・使用人その他の従業者が、その業務に関して非弁行為をした場合は、その法人や個人事業主にも「300万円以下の罰金」が科される可能性があります(同法第78条第2項)。
2、退職代行業者の業務が非弁行為に該当するケース
退職代行業者が非弁行為で逮捕されると、利用者も捜査機関から事情聴取を求められるなどトラブルに巻き込まれるおそれがあります。
退職代行業者の業務が非弁行為に該当するケースとしては、以下のような例が挙げられます。
-
(1)未払いの給与や残業代の支払いを請求する
従業員(労働者)が退職する際には、勤務先が支払うべき給与(残業代を含む)が未払いとなっているケースがあります。
未払いとなっている債権の回収業務は、債権者と債務者の間で紛争(トラブル)が発生していると考えられるため、訴訟に発展していない段階でも「その他一般の法律事件」に関するものに当たる可能性があります。
したがって、未払い給与の請求・回収は、弁護士または弁護士法人でなければ行うことができない弁護士業務に当たるため、無資格の退職代行業者が行う場合は非弁行為に該当します。 -
(2)退職の条件を交渉する
退職条件に関して、意見が異なる勤務先と従業員のいずれかを代理して交渉することは、トラブルの解決を取り扱うものであるため「その他一般の法律事件」に関するものに当たります。
たとえば退職金を上乗せしてほしい、会社都合退職扱いにしてほしいなどと交渉するようなケースが挙げられます。
こうした退職条件の交渉は、弁護士または弁護士法人でなければ行うことができない弁護士業務に当たるため、無資格の退職代行業者が行う場合は非弁行為に該当します。 -
(3)ハラスメントに対して損害賠償を請求する
ハラスメントに関する損害賠償請求を従業員の代理人として行うことは、勤務先と従業員の間のトラブルの解決を取り扱うものであるため「その他一般の法律事件」に関するものに当たります。
したがって、無資格の退職代行業者が勤務先に対するハラスメントに関する損害賠償請求を代理した場合は非弁行為に該当します。 -
(4)顧問弁護士からアドバイスを受けた程度で、法律事務を請け負っている
法律事務所(弁護士事務所)では、事務員が依頼者や相手方に弁護士のメッセージを伝えたり、形式的な事務を処理したりすることがあります。
これは、事務員が弁護士の使者として対応して弁護士の監督・指揮のもとで業務をサポートしているに過ぎず、実質的には弁護士が業務を行っていると評価できるため、基本的に非弁行為の問題は生じません。
しかし、退職代行業者が顧問弁護士からアドバイスを受けているという理由だけで、自ら法律事務を請け負っているとすれば問題があります。その場合、当該業者は独立した事業者であり、顧問弁護士の使者と評価することは基本的にできません。
そのような事情にもかかわらず、「顧問弁護士が監修している」などとして、未払い給与の請求、退職条件の交渉、ハラスメントに関する損害賠償請求などの法律事務を無資格の退職代行業者が取り扱うことは、非弁行為に当たるおそれがあります。
お問い合わせください。
3、退職代行業者を選ぶ際の注意点
退職代行業者を利用する際には、非弁行為をする違法業者を避けなければなりません。退職代行業者の選定に当たっては、特に以下のポイントに注意しましょう。
-
(1)運営元の事業者に関する情報を確認する
退職代行業者を探す際には、必ず運営元の事業者に関する情報を確認しましょう。
法律事務所と連携していることを公表している業者であれば、法令順守に配慮して運営されているケースもあります。
ただし、顧問弁護士がいるからといって、常に法的に適切な運営がなされているとは限りません。サービス内容が法律事務にあたるかどうかを見極めるためには、慎重に判断する必要があります。 -
(2)取り扱う退職代行業務の範囲に、非弁行為が含まれていないことを確認する
退職代行業者は、ウェブサイトにおいて取り扱っている退職代行業務の内容を紹介しているケースが多いです。
以下の法律事務は、上記のとおり、無資格の退職代行業者は取り扱うことができません。- 未払い給与の請求
- 退職条件の交渉
- ハラスメントに関する損害賠償請求
退職代行業務の範囲にこれらの事務が含まれていないか、業者のウェブサイトを調べて確認しましょう。
-
(3)不安な点や分からない点があれば、弁護士に相談する
退職代行サービスの内容が非弁行為に当たるか否かの判断は、弁護士法に関する十分な知識がなければ難しいです。
自分で退職代行業者を調べる中で、非弁行為に当たるかどうかの判断が付きにくい場合は、弁護士が退職代行を請け負っている事務所に依頼するのがもっとも確実です。
弁護士であれば退職サポートだけでなく、未払い給与・残業代など、退職に伴う幅広い対応が期待できます。
4、退職サポートを弁護士に相談・依頼するメリット
退職代行業者の利用を検討している方は、弁護士による退職サポートを利用することもご検討ください。
退職サポートについて弁護士に相談および依頼をすることの主なメリットは、以下のとおりです。
- 非弁行為について心配する必要がない
- 退職条件や未払い残業代などについて、会社に対する請求や交渉も任せられる
- 会社とのトラブルが発生した場合には、裁判手続きを含めた対応を依頼できる
退職は精神的な負担が大きな手続きです。トラブルに発展するリスクもありますので、弁護士による退職サポートを利用するのが安心です。スムーズに会社を退職したい方は、ぜひ弁護士による退職サポートをご検討ください。
5、まとめ
非弁行為とは、弁護士または弁護士法人でない者が、無資格で弁護士業務を行うことであり、犯罪となる可能性があります。
一部の退職代行業者は、非弁行為をしている可能性があります。退職代行業者を選ぶ際には、運営元の事業者に関する情報や、取り扱っている業務の範囲などをよく確認することが大切です。
ベリーベスト法律事務所は、弁護士による退職サポートをご提供しております。非弁行為の心配がなく、未払い残業代の請求や退職条件の交渉なども幅広く取り扱っているので安心です。
ご自身で退職の意思を会社に伝えるのに抵抗がある方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています