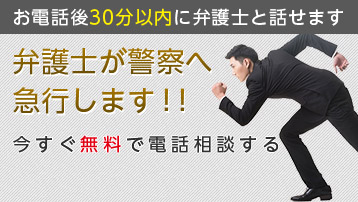コンテンツビジネスで詐欺と言われた! 怪しまれるケースと逮捕事例
- 財産事件
- コンテンツビジネス
- 詐欺

令和4年に北九州市内で発生した詐欺事件は349件でした。
インターネット上で展開されている「高収入」「高配当」を謳ったコンテンツ販売ビジネスの中には、詐欺と判断されても仕方がないようなものが紛れています。詐欺的な方法でコンテンツビジネスを行うと、逮捕・起訴されて有罪判決を受けるおそれがあるので十分ご注意ください。
本記事では、コンテンツビジネスが詐欺に当たり得るケースや、詐欺と判断された場合のリスクなどをベリーベスト法律事務所 北九州オフィスの弁護士が解説します。


1、コンテンツビジネスが詐欺に当たり得るケース
コンテンツビジネスとは、コンテンツ(=著作物)を活用し、集客・販売を行うビジネスモデルです。コンテンツも様々であり、顧客を騙すような形でコンテンツビジネスを行っていると、詐欺罪(刑法第246条第1項)によって逮捕・起訴され、有罪判決を受けるおそれがあります。詐欺罪は、「人を欺く」ことによって人を誤信させ「財物を交付」させた場合に成立する可能性があります。
例えば、本来必要のないものを、言葉巧みに購入させた場合には、「人を欺」いて必要があると誤信させて「財物を交付」させたといえるので、詐欺罪が成立する可能性があるのです。詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
特に、高額なのに内容が薄い情報商材を購入させる行為や、詐欺的な投資スキームへの参加を勧誘する行為などは、上記の例のように、詐欺に当たると判断される可能性があるのでご注意ください。
-
(1)高額なのに内容が薄い情報商材を購入させる
インターネット上では、副業や投資などに関して、さまざまな内容の情報商材が販売されています。
情報商材を販売すること自体は自由です。また、情報商材の中には、価格に見合った有用なものもあると思われますので、情報商材を販売することが、直ちに詐欺罪に問われるというわけではありません。
しかし、購入者に高額の代金を支払わせておきながら、それに見合った内容の情報を提供せず、どこでも入手できるような薄い情報を提供するにとどまる場合は、詐欺を疑われるおそれがあります。
特に、詐欺的な情報商材の代金が高額であればあるほど、財産への被害が大きいため、悪質であると判断され、重い刑罰が科される可能性が高まるので十分ご注意ください。 -
(2)詐欺的な投資スキームへの参加を勧誘する
情報商材を購入し、または無料配布を受けた顧客に対して、詐欺的な投資スキームへの参加を勧誘する例が見受けられます。
たとえば、プロが運用すると偽って集めた資金を別の参加者への配当へ横流ししたり(=ポンジ・スキーム)、投機的な取引に使い込んだりするケースが典型例です。このような詐欺的な投資スキームへの参加を勧誘すると、主宰者から末端の実働部隊に至るまで、芋づる式に詐欺罪で摘発される可能性があります。したがって、勧誘を行った者についても、実行犯あるいは共犯として、詐欺罪に問われる可能性があるのです。
投資詐欺は被害額が大きくなり、被害者の数も多くなる傾向にありますので、末端者であっても実刑判決を受けるおそれがあるので注意が必要です。
2、コンテンツビジネス詐欺に関連する犯罪行為
コンテンツビジネス詐欺に関連して、以下のような行為をすると、詐欺罪以外の犯罪によっても処罰される可能性があります。
金融庁の登録を受けることなく、投資スキームへの参加を勧誘し、投資助言を行い、または他人から集めた資金を運用すると、金融商品取引法違反によって処罰されます(金融商品取引法29条)。
無登録による金融商品取引業の法定刑は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」で、懲役と罰金が併科されることもあります(同法第197条の2第10号の4)。
また、法人に対しても両罰規定によって「5億円以下の罰金」が科されます(同法第207条第1項第2号)。
② 有印公文書偽造罪・偽造公文書行使罪
顧客を騙す目的で、公務所または公務員の印章や署名を使用して、公務所または公務員の作成すべき文書や図画(=公文書)を偽造した場合は、有印公文書偽造罪によって処罰されます(刑法第155条第1項)。
また、顧客を騙すために偽造公文書を行使した場合は、偽造有印公文書行使罪によって処罰されます(刑法第158条第1項)。
有印公文書偽造罪と偽造有印公文書行使罪の法定刑は、いずれも「1年以上10年以下の懲役」です。なお、偽造有印公文書行使罪は未遂であっても処罰されます(刑法第158条第2項)。
③ 有印私文書偽造罪・偽造私文書行使罪
顧客を騙す目的で、他人の印章や署名を使用して、権利・義務・事実証明に関する文書や図画(=私文書)を偽造した場合は、有印私文書偽造罪によって処罰されます(刑法第159条第1項)。
また、顧客を騙すために偽造私文書を行使した場合は、偽造有印私文書行使罪によって処罰されます(刑法第161条第1項)。
有印私文書偽造罪と偽造有印私文書行使罪の法定刑は、いずれも「3か月以上5年以下の懲役」です。なお、偽造有印私文書行使罪は未遂であっても処罰されます(刑法第161条第2項)。
3、コンテンツビジネス詐欺で逮捕される可能性はどのくらい?
最近では、コンテンツビジネスに名を借りた詐欺的な行為が横行しており、被害者も急増している状況です。そのため、特に多くの被害者を生むような詐欺行為や、被害額が大きい詐欺行為については、コンテンツ販売者が逮捕される可能性が高まっていると考えられます。実際に、コンテンツビジネス詐欺によって逮捕、有罪になったケースも散見されます。
コンテンツビジネス詐欺の疑いで逮捕されると、長期間にわたって身柄が拘束される上に、最悪の場合は刑務所へ収監されることになりかねません。コンテンツビジネスを行うのであれば、顧客を騙すようなことはせず、クリーンな運営に努めましょう。
4、コンテンツビジネス詐欺に関する刑事手続きの流れ
警察によってコンテンツビジネス詐欺の疑いをかけられて逮捕される場合、以下の流れで刑事手続きが進行します。
-
(1)逮捕~起訴前勾留
警察官は、裁判官による逮捕状の発付を受けた後、コンテンツビジネス詐欺の被疑者を逮捕します。
逮捕の期間は最長72時間で、その間に警察官や検察官による取調べが行われます。逮捕期間中は家族などとの面会が認められませんが、弁護士とは面会することができます。
検察官が逮捕後も引き続き身柄を拘束すべきと判断した場合は、裁判官に対して勾留請求を行います。
勾留請求が認められると、さらに最長20日間、勾留によって被疑者の身柄が拘束されます。勾留期間中も、複数回にわたって警察官や検察官による取調べが行われます。
勾留への移行後は家族などとの面会が認められるケースが原則ですが、例外として、共犯者がいる場合等には、接見禁止処分が行われ、引き続き面会が禁止されることもあります。接見禁止処分がなされた場合も、弁護人とは引き続き面会することが可能です。 -
(2)起訴・不起訴
原則として勾留期間が満了するまでに、検察官は被疑者を起訴するか否かを決定します。
起訴された場合は、被疑者から「被告人」へと呼称が変更され、起訴後勾留に移行して引き続き身柄が拘束されます。不起訴となった場合は、直ちに被疑者の身柄が解放され、刑事手続きが終了します。 -
(3)起訴後勾留・公判手続き
起訴後勾留への移行後は、弁護人と相談しながら公判手続き(刑事裁判)の準備を整えましょう。
また、起訴後勾留期間中は、裁判所に対して保釈を請求することができます。保釈が認められると、保釈保証金を預けること等を条件として、一時的に身柄が解放されます。
起訴されてからおおむね1か月後を目安に、裁判所の法廷において公判手続きが開催されます。公判手続きは、検察官が犯罪事実を立証し、被告人がそれに対して反論する形で進行します。
被告人の方針は、罪を認めて情状酌量を求めるか、または罪を否認して争うかの2通りに分かれます。 -
(4)判決・刑の執行
公判手続きの審理が熟した段階で、裁判所が判決を言い渡します。
すべての犯罪要件が認められた場合に限り、有罪判決が言い渡されます。有罪判決の場合は、量刑や執行猶予の有無も示されます。犯罪要件が一つでも不認定となった場合は、無罪判決が言い渡されます。無罪判決の場合、被告人の身柄は釈放されます。
第一審判決に不服がある場合は、高等裁判所に対して控訴をすることができます。控訴審判決に不服がある場合は、最高裁判所に対する上告が認められています。控訴・上告の期間は、いずれも判決の言渡しを受けた日の翌日から起算して14日間です。
有罪判決が確定した場合は、原則として刑が執行されます。ただし、刑の全部に執行猶予が付された場合は、刑の執行が一定期間猶予されます。
5、警察にコンテンツビジネス詐欺を疑われたら、弁護士に相談を
コンテンツビジネス詐欺の疑いで警察に取調べを求められたら、後に逮捕される可能性がありますので、早い段階で弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、取調べへ臨む際の心構えや注意点などについてアドバイスを受けられます。逮捕されてしまった場合でも、事前に弁護士へ相談していれば、速やかに接見(面会)へ来てもらうことができます。家族と面会ができない状況でも、弁護士を通じて家族とやり取りすることができるので、精神的な支えになるでしょう。
また弁護士には、早期の身柄解放に向けた活動や、公判手続きでの弁護活動も依頼できます。重い刑事処分を回避するためには、弁護士のサポートが欠かせません。
コンテンツビジネス詐欺の疑いをかけられたら、速やかに弁護士へご相談ください。
お問い合わせください。
6、まとめ
顧客を騙すようなコンテンツビジネスを行っていると、詐欺の疑いで警察に逮捕されるおそれがあります。
もしコンテンツビジネス詐欺の疑いをかけられたら、刑事弁護について速やかに弁護士へ相談しましょう。ベリーベスト法律事務所 北九州オフィスは、刑事弁護に関するご相談を随時受け付けております。警察から取り調べを求められたらお早めにご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています