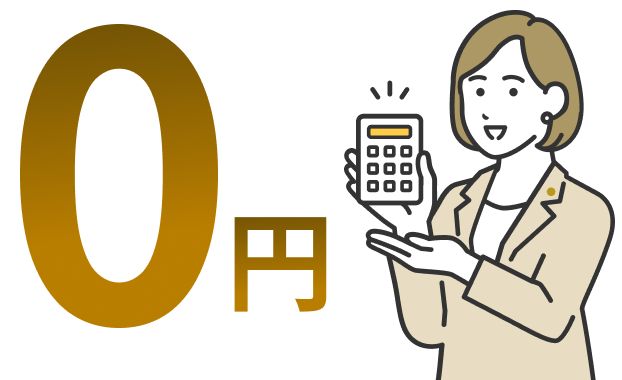父親の相続について遺留分を主張するにはどうする?
- 遺産を受け取る方
- 遺留分
- 親

北九州市をはじめ、九州地方全体を管轄下に置く福岡高等裁判所では、平成29年5月、遺留分減殺請求と特別受益をめぐった争いについての判断がなされました。平成30年に成立した相続法分野での改正でも、遺留分に関する変更があります。
遺留分は、相続に関する制度です。たとえば父親が亡くなり、配偶者である母親、長男、次男の3人が残された場合、この3人が法定相続人です。このとき、父親が「財産のすべてを次男に相続させる」という遺言を残していたとしましょう。このとき、母親や長男は、相続財産を一切手にできないのでしょうか?
確かに、法的に正式な書式で書かれた遺言書であれば、ある程度の強制力はあります。しかし、長男や母親は、遺留分という権利を主張するという方法があるため、相続財産から受け取ることが可能になるのです。
この記事では、遺留分の特徴や主張方法について解説します。
1、遺留分は残された家族に認められた最低限の取り分
「遺留分」とは、一定の相続人であれば必ず受け取れることが保障された、相続財産における一定の割合を指します。
自分の財産は、自由に処分したいと思われるでしょう。実際に、私的財産制度という制度があり、生きているときには、自分の財産を好きなように売ったり買ったりすることができます。さらに、自分が亡くなったあとについても、自分の財産を自分の好きなように処分することができる権利があります。亡くなる前に「被相続人」として財産の処分や分配についての権利を主張し、法的な強制力を持たせる手段が「遺言書」です。
一方で、相続できる財産を築いた「被相続人」の夫が働いてこられたのは、家事や育児など、そのほかの家族によるサポートがあったおかげでもあります。よって、「相続人」たる親族は被相続人の財産形成のために力を尽くしてきた、という解釈ができるとされています。
相続人の権利と、被相続人の権利、このふたつの均衡を図るために、遺族には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の取り分が認められています。逆にいえば、遺留分以外の財産の処分については、個人が自由に定めることができるのです。
もともと「遺留分」は、家族の生活の保証のために作られた制度といわれています。民法が制定されたころの日本では、現代のように女性はフルタイムどころか働くことも難しい状況にありました。そのため、夫が亡くなってしまい、子どもが働いていないなどのケースは、生活基盤としての収入が失われてしまう事態に陥ってしまっていたのです。
以上を踏まえ、遺留分の割合については、次のように定められています。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
- 直系尊属のみが相続人である場合……被相続人の財産の3分の1
- 前号に掲げる場合以外の場合……被相続人の財産の2分の1
ここに規定されているとおり、兄弟姉妹には遺留分がありません。法律ができた当時の社会情勢では、基本的に兄弟姉妹はそれぞれ結婚したあと、別々の世帯を形成されることが一般的でした。「生涯にわたって兄弟姉妹と一緒に居住し、財産形成に寄与した」というケースはまれだと考えられていたためです。
2、遺留分の特徴は?
遺留分を受け取るためには、権利の主張が必要です。
特に遺言書が残されていない状況下における法定相続の場合は、何も意思表示をしなければ、そのまま法定相続人として、相続分を相続することになります。相続財産に負債というマイナスの財産が多い場合も同様です。遺言書にもとづいて相続する場合も、何も主張しなければ、遺言書どおりに遺産が分配されます。
しかし、遺留分だけは、主張しなければ権利として認められないのです。さらに、遺留分を主張できる期限も、民法1042条で設定されています。
<遺留分を主張できる期限>
- 相続の開始および減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った日から1年以内
- 相続開始のときから10年以内
「相続の開始」は、被相続人が死亡したことを知ったときなどを示します。また、たとえ死亡の事実を知らされず、「相続開始」したときがわからなかったとしても、死亡から10年経過してしまうと遺留分の権利主張ができなくなってしまいます。
また、遺留分は放棄をすることも可能です。遺留分を放棄するという意思表示をすれば、1年の時効を経過しなくても、遺留分の主張ができなくなります。
遺言書で「遺留分を放棄して欲しい」という記載があるケースもあるでしょう。その記載に従う必要は、もちろんありません。相続の分配方法を財産の持ち主が自由に決められるのと同じように、遺留分の権利をどうするかは、遺留分を持つ人の意思で決めることができます。
3、実際にどう遺留分を計算する?
では、実際にどのように遺留分を計算していくのでしょうか。遺留分の権利は、前述のとおり、明確に定められています。
- 親や祖父母など、直系尊属のみが相続人である場合……被相続人の財産の3分の1
- 妻や子が相続人であるなど、前記以外の場合……被相続人の財産の2分の1
遺留分の対象となる財産は、プラスの財産もマイナスの財産も含めてすべてになります。そのうえで、「相続人全体の遺留分割合」と「相続人それぞれの遺留分割合」について考える必要があります。
民法1029条1項によると、遺留分は、「相続開始時」、つまり、被相続人が死亡したときにあった相続財産の価額に、贈与した財産の価額をプラスし、債務の全額を控除して計算します。
具体的に各相続人の個別遺留分割合の計算式は、以下のとおりです。
法定相続割合とは、特に遺言書などがなかったときに分割するために定められた割合です。具体的には、民法第900条に定められています。たとえば被相続人の配偶者であれば、2分の1ですし、さらに被相続人に子どもがふたりいるときは、兄弟姉妹の法定相続割合を均等に分割することになるため、子どもひとりあたり4分の1が法定相続割合になります。
では、具体的に考えてみましょう。冒頭に登場した両親と子どもふたりの家庭では、父親が亡くなったとき、「父親が次男に全額相続させる」旨の遺言をしていました。そのうえで、たとえば、相続財産は1000万円で、生前に次男に不動産を購入する資金として200万円渡していた場合、遺留分はどれくらいになるでしょうか。
マイナスの財産が0の場合は、1000万円に200万円足した額が相続財産の金額となります。相続人は被相続人の妻と、ふたりの子どもです。個別遺留分割合の計算をすると、母親は4分の1、子どもはひとり8分の1の遺留分があります。
つまり、母親は300万円、長男は150万円、遺留分を主張できるわけです。もし、すでに次男がすべての遺産を手に入れているあとであれば、それぞれの金額を次男に請求することが可能となります。もし、預金がなく、不動産しか残っていない場合は、次男は金銭で遺留分を支払うか、不動産を共有名義にする必要があるでしょう。
ただし、2019年7月以降に施行予定の法改正によって、今後、相続に関するルールが変更されます。たとえば、婚姻期間が20年以上の夫婦がいる家庭で、居住不動産があるケースの特例ですが、配偶者保護のための方策が行われることになることが決まっています。
4、遺留分を主張するための手段の流れは?
遺留分を侵害した遺言が見つかったとき、どのように対応すればいいのでしょうか。流れをみていきましょう。
-
(1)遺言書は有効かどうか
遺言書が、自分の遺留分を侵害した内容になっていた場合にまずすべきことは、本当にこの遺言が被相続人の意思によるものなのか調べることです。
たとえば、自筆証書遺言の場合は、現行の民法では被相続人本人による手書きで書かれていなければ無効となります。まずは、目で見て本人の筆跡ではないと思ったときや、遺言書が書かれた日付が不明なときなどは、その有効性を争うことを検討しましょう。秘密証書遺言の場合も、改ざんなどを疑い、チェックしてみるとよいでしょう。
また、公正証書遺言の場合も、遺言書の作成時に病気で正常な判断能力がなかったというときには、これを理由に争うことを検討しましょう。 -
(2)遺留分を主張する相手方は誰?
遺言書が本人の意思によって作られたものだと判断された場合、そのままでは、遺言書に書かれた内容で遺産相続がなされてしまいます。まずは、遺言書のままでよいのか、遺留分を受け取るべきかを検討してください。
遺留分を受け取りたいと考えたときは、自分の取り分を主張するために遺留分の権利行使を表明することになります。
権利行使の表明は、適切な相手方に対してでなければなりません。遺留分を主張することができる相手は、以下のような受遺者や遺留分を侵害した者です。
- 遺贈を受けた人(受遺者)
- 死因贈与を受けた人
- 生前贈与を受けた人
-
(3)遺留分を主張する
遺留分は、主張できる期限があります。期限を過ぎてしまうと、時効が成立するため、権利の主張ができなくなってしまいます。
権利を主張することの意思表示を行うとともに、この日にきちんと意思表示をしたという第三者機関の証明をするため、主張する際は内容証明郵便を利用してください。内容証明郵便によって権利を主張しておけば、主張した日付が記録されるため、明確になります。後日、相手方が「時効によって遺留分の権利が消滅している」という主張をする可能性もありますが、内容証明郵便を使うことで、あらかじめ防止することができます。 -
(4)協議する
遺留分を主張することで、相手方は何らかの対応を迫られることになります。可能な限り、話し合いを通じて解決を図っていくほうがよいでしょう。この話し合いのことを協議と呼びます。
もし、多忙などの理由で、直接顔を合わせて話し合いする時間を作れないというときなどは、弁護士などに依頼して代わりに話し合ってもらうこともできます。 -
(5)調停を起こす
話し合っても解決しないような場合や、相手方が話し合いに応じてくれないような場合は、調停を起こして第三者機関となる家庭裁判所に介入してもらい、話し合いを進めることになります。
調停は裁判ではなく、調停員という第三者を介して話し合いをする場です。審判を下す裁判のように、最終的な決断をしてくれる場所ではありません。調停も、弁護士であれば、あなたの代理人として対応してもらうことができます。 -
(6)遺留分減殺訴訟を起こす
調停でも問題が解決しない場合には、遺留分減殺訴訟を起こすことができます。裁判は専門知識が必要とされる手続きのため、弁護士に依頼することをおすすめします。
5、まとめ
遺言書などの存在によって相続することができなくなってしまった場合でも、あきらめる必要はありません。相続しないと生活できないなどの場合には、積極的に遺留分を主張する道があるのです。
ただし、遺留分の主張には期限があります。相手方が話し合いに応じないうちに時効が到来し、権利の主張ができなくなる可能性もあるでしょう。どうすればスムーズに話し合いができるか、遺留分の主張をどのようにするべきか、わからないこともあるでしょう。
遺留分の主張や相続人同士の争いでお困りなら、ベリーベスト法律事務所 北九州オフィスまでご連絡ください。北九州オフィスの弁護士が力を尽くします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています